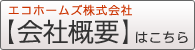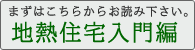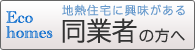アイヌの伝統民家「チセ」
宇佐美智和子(SOLAR CAT 1999 Winter no.37より)

民家とその住まい方には、永い歴史の中で育まれ磨かれた、その地域特有の工夫が見られます。
アイヌの伝統的な住居である「チセ」には、厳寒の地で生きていくためのどのような知恵が培われていたのでしょうか。
市立旭川郷土博物館と共同で、その解明に着手したのは、1981年でした。
まず、復元標本住居のチセで、アイヌの長老より聞き出した防寒対策を施して宿泊体験し、それによって疑問が生じ、改めて文献や資料を調べて実験測定をする。そしてまた宿泊体験をするという作業を繰り返し、生活が営まれたチセの室内環境が、10年近くかかりましたが、ある程度明らかになりました。

図1:ポロチセの断面図/チセは堀建て丸太柱構造で、屋根は寄棟、棟の両側は急勾配になっている。葺き材は地域差があり、茅、芦、木の皮、笹が使われる。市立旭川郷土博物館がアイヌ文化の森「伝承のコタン」に復元したポロチセは笹葺きである。
笹葺きチセ
マイナス41℃の日本最低温度記録を持つ北海道上川地方(旭川市周辺)のチセは、屋根も壁も笹葺きで、その厚みは笹の葉の長さに制約されて20cm程度だったようです。
このアイヌのチセが、比較的しのぎやすい住居であったと推測される記録が残されています。
日本スキーの父といわれるテオドール・フォン・レルヒの『明治日本の思い出』(中野理訳)の中に、「私が酷しい冬の、それは1912(明治45)年の2月のことであった。はじめてこの村をたずねたとき、驚いたことにはどの家も空っぽで物置として使われている。そのかわりに家の傍にたてられたヒュッテ(註:チセ)に住んでいた。」「シベリア的嵐の場合には吹きさらしの軽い日本の小屋よりは確かに暖かい」と、書かれています。
レルヒが記している「物置として使われている家」とは、旧土人保護法によって、明治40年より当時の旭川町がアイヌに給付した50戸の新築木造住宅のことです。
「寒くて住みにくい」との理由で、移転後間もなく、各戸この住宅に隣接してチセを建てて移り住んだとの調査報告があります。
また、この中に、アイヌの古老から聴取した、「チセは夏涼しくしのぎやすく、冬は暖かかった」との記録も見受けられます。

写真2:復元中のポロチセ。屋根、壁のすべてが笹で葺かれるが、壁は柱の外側に横木を15cm〜20cm間隔で縛り付け、これに笹の葉の部分を戸外に出して、下から葺く。
 写真3:笹は3本ずつ束ねて葺かれる。戸外の笹の葉は鳥の羽のように重なり合って雨水の浸入を防ぐ。 |  写真4:室内側から見た笹葺き。簾のように整然と葺かれている。 |

図2:ポロチセの小屋伏図

図3:ポロチセの平面/チセの中でも大型のものをポロチセという。チセの平面構成はどの地方もほぼ共通していて、出入口には玄関、物置、作業場を兼ねた納室(セム)があり、母屋には平側に二つの窓、奥の壁にひとつ神窓がある。窓には笹で編んだ戸が、チセの入口、セムの入口には莚が吊される。母屋の中央には炉が切られ、火は一年を通じて絶やさない。土座は表面に葦を敷き詰め、その上に茅で編んだソッカラを置き、さらにその上にキナという蒲の葉で編んだ柔らかい敷物を敷く。
笹葺きチセの防寒対策
復元標本住居であるチセであっても、収集した伝統の防寒対策を念入りに施して宿泊体験すれば、かなり暖かいのではないか、との期待をもって下記の準備をしました。
・ 外からの出入口だけを残して、チセの外周に雪をよせ、約1mの雪の壁をつくる。
・ 雪屋根は積雪のままとし、雪が少ない時は、50〜60cmの雪を置く。
・ 壁面の窓を壁材料と同じ笹でつくった蓋で閉鎖し、壁面全体(窓も含む)を数mある長い花ゴザ(チタラベ)で巻き覆う。
・ 外からの入口と母屋への入口に、ゴザ(キナ)を三枚互い違いに重ねて吊るす。
最初の宿泊体験
〜生活できる温熱環境ではなかった〜
1982年2月、防寒対策したチセで、宿泊前の3日間、囲炉裏で薪を燃やして予熱し、「寒ければ燃やせばよい」と薪を山ほど積み込み、冬山用シェラフなど準備万端整えて、市立旭川郷土博物館の青柳信克学芸員が、初めての宿泊体験に、まず一人で挑みました。
朝かけつけた私は、前夜帰る時と質の違う、初めて体験する「耐えられない寒さ」に驚きました。
前夜の夜、外気温がマイナス5℃の時、座っている場所の温度は10℃程度ありましたが、朝外気温度がマイナス17℃になった時には、囲炉裏の傍の同じ場所が、薪を燃やせば燃やすほど、ますます温度が下がってマイナスになり、背中に強い冷気流が襲ってきました。燃えることによって、冷たい外気を吸引していたわけです。見上げると、多量の薪燃焼によって、断熱材であるはずの屋根雪の棟部分がぽっかり開いていました。
もし、外気がマイナス30℃程度まで下がれば、燃やす量に比例して囲炉裏をめがけてマイナス30℃の冷気が襲い、燃焼空気は勢いの強い上昇気流となって、雪の融けた屋根から出ていたはずです。
「寒ければ燃やせばよい」という暖地の採暖の意識が、まったく通用しない環境だったのです。
雪が融けない程度しか薪は燃やせない
文政5年の『北夷談』に、雪に埋もれたチセでの小事件が書かれています。朝飯を食べているところへ、膳の上に窓から犬が落ちてきた。
雪が降り積もってチセが埋まって平地のようになり、「夫ゆえ外は大荒大風にても、内に居れば風あるとも知らず、たきび焼火はあり、暖にしてしのぎよく、これゆえに犬も平地を常のごとくに狂ひ遊びて、我しらず窓へおちしと見ゆ」と。
不思議なことに、この『北夷談』では、たき火をしているのに雪が融けていません。宿泊体験からも、断熱材の雪が融けると生活できる環境ではなくなることがわかりました。
「雪が融けない程度に薪を燃やすこと」でしのげる厳寒地の室内環境とは、いったいどのようなものなのでしょうか。
室温と体感温度が乖離した温熱環境
〜室温は5℃。体感温度は20℃〜
最初の宿泊体験のチセは、地面に直接の転がし根太に床を張ってあり、その上に寝ましたが、朝床を少し剥がして見ましたら、氷がびっしり張り付いていました。アイスバーンの上に寝ていたことになります。
昭和57年の『朝日新聞』に、青木愛子さん(当時68歳)は、「昔のチセは暖かかった」「チセも明治になって、「新しがり」のつもりで床を板張りにしたところは寒く、アイヌも風邪を引きやすくなったといわれている」と述べています。
そこで、1983(昭和58)年には、床板を剥がして、17日間日中だけですが、連日燃焼しました。加熱していない期間は、夜間外気温が10℃下がると土間表面温度は5℃下がるという割合でしたが、日中加熱を始めた初期には夜間に3.5℃、加熱末期には2℃の割合でしか下がらなくなりました(数年後、床造りして連日加熱した冬は土間温度は下がりませんでした)。
この加熱期間の午前9時から午後6時の平均温度は、外気温度マイナス4.7℃、室温5.1℃、静気中の体感温度を表すといわれる黒球温度が20.0℃となっています[図4]。
実際は気流がありますから、体感温度は20℃よりやや低かったと推定できますが、室温が5℃であるのに、体で感じる温度は、室温より15℃も高い20℃であるとはどういうことでしょうか。
それはチセの内部が、室温は低くても、薪が燃えることによる強い放射熱や、その熱を再放射する植物材の壁面と床面からなっており、床面は、蓄熱しておだやかに放熱している土間床温度にも支えられて、室温よりも放射熱が優秀な温熱環境となっているからです。
体感温度は、気流が少ない時は、空気の温度と周囲の表面温度(=放射熱)が同じ比重で私たちに作用します。つまり、体で感じる温度は、室温と周囲の放射熱との平均温度なのです。
現代の住宅は、室温が20℃でも外気温が低いと窓や壁や床の表面温度が室温より低くなっています。もし表面温度が10℃程度しかなければ、体感温度は15℃しかありません。冬の室温が20℃では物足りなく感じるのは当然です。
薪を燃やしているチセの体感温度が20℃室温が5℃ということは、(5℃+□℃)÷2=20℃ですから、放射温度は35℃ということです。

図4:1983年冬、17日間日中だけ薪を連続燃焼したときの14日目のチセ内の温度変動/当日の最大燃焼時である17時30分(左から2番目の山)での座位の高さ(50cm)の温度を見ると、室温が6.5℃であるのに対し、囲炉裏から2〜3m離れた周壁面温度は10℃を越え、黒球温度は20℃を越えている。室温と体感温度が乖離した温熱環境にあることがわかる。
土間床への蓄熱
半月余り、わずかに薪を日中のみ燃やし続けただけで、チセ室内はかなりしのぎやすくなりましたが、その後の宿泊体験で、夜間に外気がマイナス30℃に迫った時は、身の危険を感じるほどチセ内の温度が下がり、薪を燃やそうにも燃え上がらないでくすぶるだけという恐ろしい一時がありました。しかし子育てをしていた生活の場が、このように寒かったはずはありません。
北海道大学の荒谷登教授(現名誉教授)にデータを見て頂き、ご指導を仰ぐと、「地下室でも、温度が上がりきるには1年はかかる」とのこと。一方、「アイヌは夏でも火を絶やさず燃やし続けた」との記述が数箇所で見つかりました。
そこで、1985年夏から1986年春まで、加熱チセと比較チセの2棟について、地中温度も含め比較観測しました。薪連日燃焼実験は、諸般の事情から、11月下旬から2月上旬までで、薪燃焼はそれまでと同じ日中だけとなりました。
伝統の床造りは、土間の表面に葦を敷き詰め、その上に茅で粗く編んだスノコ状のソッカラを置き、さらにその上にキナ(蒲の葉で編んだ柔らかい敷物)を敷いて完成します。
それまでの実験測定の床は、板敷か、それを剥がした土間床でしたが、長期測定では、正式に伝統的な床造りをすることにしました。しかし、その材料集めに手間取り、床作りができないので加熱実験を開始することができません。とりあえず床作りしないまま11月22日から日中の薪燃焼を始めました。そのため「年中火を絶やさないアイヌに実生活」とは遠いものになってしまいました。
12月5日床造りが完了。予想以上に厚く植物材で覆われた地面に、薪の炎が消えない程度のささやかな燃焼熱が届くのだろうかと気をもむ間もなく、それまでは、室温が上下するに連れて土間表面の温度も大きく変動し、夜間から朝までマイナス温度になっていましたが、床造りを終えるや、室温が下がっても、地表面の温度は下がらず、数日で、地表面と地下10cmの温度は、常にプラス2℃前後で安定している地下30cmの地中温度と同じになりました。
その後、最寒期を迎えても地中温度は、2℃レベル以上を維持し続けました。床造りは、そのクッション性のためというより、むしろ、土間床温度を冷え込ませないための必須要件であることがわかりました。
火を消した夜間には、急激に外気温が下がりますので、入口をムシロで仕切られただけのチセ内は、マイナス20℃やマイナス30℃の寒波にさらされると、日中の加熱分は跡形もなく消え去ると思われます。
しかし、朝の火入れ前のチセは、何事もなかったかのように、いつもと同じほんのりとした穏やかな暖かさで迎えてくれました。加熱していない比較チセは、外とあまり差がありません。チセの温熱環境を支えている地中温度が比較チセよりも、7℃も高くなっているのです。
雪が融けない程度薪を日中だけ燃やし続けることによって、加熱開始時の初冬の地中温度を保ち続けていますから、外気の低下にともなって、地中温度差は加熱初期は2℃程度でしたが中期には3.5℃、末期には7℃近くも広がりました。[図5]

図5:微弱加熱による土間への蓄熱の効果/微弱加熱を始める前のチセの地温(地下10cm)はまったく同じである(11月1日)が、加熱開始後次第に差が表れ、加熱末期には7℃の差が出ている。
無尽蔵とも思えるこの熱はいったい何でしょうか?深い地中温度の経過を気象台で調べることにしました。しかし、50年余り地中温度は測定されていないとのことで、古いデータだけが保管されていました。
明治時代から1940年代まで、現代のような便利な温度センサーのない時代に、日本各地の気象台で地下10m(地域によっては5m)までの各深度10箇所について、昼夜測定し続けられていたのです。
そのことに、言葉にならないほどの深い感動を覚えました。そして同時に、現代は、センサーを一度埋め込むだけで自動的にデータが取れるにもかかわらず、測定が中断されたままになっている事実。文脈から外れますが、これは、人類を育んできた大地への関心の薄れの表れでしょうか?20世紀末に日本文化が到達している座標店を象徴的に示されたように私は受け止めました。
さて、凍てつく寒さの中で、測定し続けた数多くの方々の努力の結晶である地中温度の数値をグラフ化した時、予想もしていなかった貴重なメッセージが浮かび上がりました。〜地下5mは、夏と冬が逆転している!〜
大地の恵みと薪継続燃焼との相乗効果
地下5mの温度は、年間で冬最高温度・夏最低温度で経過していたのです[図6]。夏と冬の逆転です。これは、夏の熱が地下5mに届くのに、半年かかることを示しています。
夏が暑い旭川では、冬季の月平均気温がマイナス10℃の時に、地下5mには夏の熱が10℃になって蓄えられているのです。大地は、熱や冷熱を半年先まで持ち越す力を持っているといえるのでしょう。冬の真下には夏がいる。雪が融けるや否や地中から新しい命が甦るのは、この大地の恵みによる営みなのでしょう。
薪燃焼による蓄熱とは桁外れの無尽蔵の大きな熱に支えられていると感じたのは、地下5mから放射されていた10℃の「夏からのプレゼント」だったようです。
断熱性能の高い雪に覆われたチセ内は、床造りによって土間面からの冷え込みを抑え、ささやかながら、薪の日中の継続燃焼で室温の低下を防ぐことによって、地下5mからの10℃の支えを、土間面において約2℃でキャッチし、外気が低下しても、一冬中、その温度レベルを維持し続けています。
気象台による旭川の地下1mの冬の温度が2〜3℃であることから、今回の加熱実験では、チセの土間温度が、地下1m近傍の地中温度と定常状態になっていたと推定されます。
この実験が、夏から床造りをして、夜も火を絶やさず燃やし続けることができたら、真冬に10℃ある大地の恵みと、継続燃焼の蓄熱との相乗効果で、地下5m〜土間床まで、10℃近い大蓄熱層となり、アイヌの実生活に近づくことができたのではないでしょうか。

図6:地温と地中温度の年間変動(旭川地方気象台)/地下5mは夏と冬が逆転している。

写真5:ポロチセ。左側が納室(セム)。屋根雪は自然の積雪のままである。柱が外ふんばりであること、小屋組が三角錐形に丸太を組んだチセ特有の構造であるため、2mの積雪に耐える。


写真7:宿泊体験中のチセ内部。周壁内面に花ゴザ(チタラベ)を吊す。
生活が営まれた冬のチセの温熱環境
昔の生活が営まれていた冬のチセは、外気緩衝空間(風除室・物置・作業場・入口を兼ねる)と母屋からなるチセ全体を雪で厚く断熱して、それが融けない程度の微弱継続薪燃焼をすることによって、床造りした土間床が、夏からの熱を蓄えている大地と熱的に一体となっていたと推定されます。
その安定した地中温度に支えられた土間床温度と、薪燃焼の放射熱および周壁面からの再放射など、圧倒的に放射熱の優勢な温熱環境を形成していたため、雪が融けない程度の低い室温にもかかわらず、常に一定温度以上の体感温度を得られる住まいになっていたわけです。
屋根も壁も笹葺きという、断熱性能が期待できない住まいを、その住まい方によって、大地の恵みに支えられた見事な暖房空間にさせることができたのは、命に関わる体験を通じて得られた伝統の知恵をアイヌの人々が大切に伝承してきたからです。
19世紀まで永い生活体験で培われてきた、その気候風土特有の伝統の知恵が、20世紀の多様な文化の洗礼を受けて、その価値を確認できないまま消え去ろうとしています。
21世紀の理想の住宅は、エコロジー住宅の原点である伝統住宅の中に潜む、脈々と継承されてきたその意味の延長線の方向にあるのではないでしょうか。
(うさみ・ちわこ 玉川住宅総合研究所主任研究員)